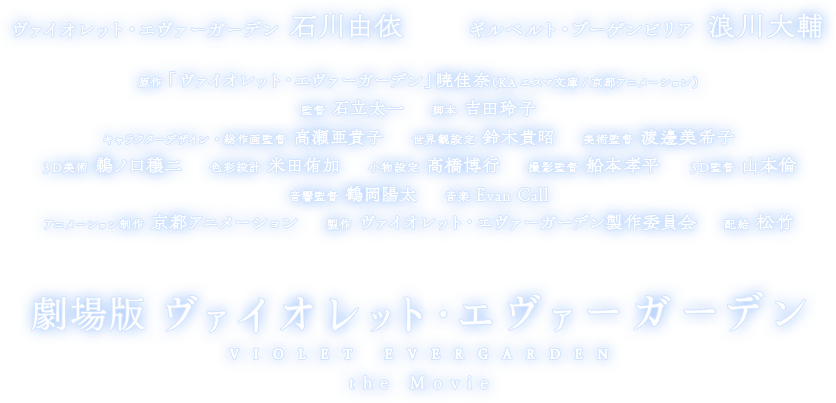スタッフトーク付き上映会
<MOVIX京都 ドルビーシネマ版 先行上映>オフィシャルレポート
※本レポートには『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の本編の内容が多く含まれます。ご鑑賞後にお読みいただくことをお勧めいたします。
2020年11月12日、MOVIX京都にて『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』スタッフトークが開催されました。登壇者を1部・2部に分け、『劇場版 ヴァイオレット』の制作にまつわる深いこだわりをご紹介しました。
第1部に登壇したのは、監督・石立太一さん、演出・小川太一さん、色彩設計・米田侑加さん、美術・篠原睦雄さんです。
スタッフトーク第1部
――皆さんの仕事の内容について教えてください。
石立:監督は、作品の制作現場における最終責任者です。まず、各制作スタッフに作品の向かっていく道筋を示し、それに基づいて各セクションで素材が作られていきます。そして、出来上がった絵をチェックしつつ、それらを全て集合させたときに、定めた目的に対して正しくその形を成すものに仕上がっているかどうかを確認していきます。
小川:演出は、石立監督の思い描くイメージをより具体的な実作業に落とし込んでいくために、各スタッフに言葉を尽くして共有するオペレーターのような役割を担います。『劇場版 ヴァイオレット』では、石立監督も演出として多くのカットのチェックをされたので、なるべく同じ目線で見て、石立監督が思い描くイメージを共有するように心掛けました。あとは、石立監督に色々と茶々を入れる役割をしていたと思います(笑)。
米田:色彩設計は、主に作品の舞台や世界観に合ったキャラクターや小物の色を考えていく仕事です。また、季節、天候、時間帯などの状況に合わせて色を変えていく「色変え」という作業も行っています。劇中の色は、色彩設計一人だけで決めているのではなく、別に「色指定スタッフ」がいて、分担してカットごとの色を作っていきます。色彩設計は、分担して作ったものをチェックし、作品として一貫性を保てるように全体の色の管理を行っていきます。
篠原:僕は美術監督ではないのですが、美術担当として、『劇場版 ヴァイオレット』では、TVシリーズ、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-』(以下、『ヴァイオレット 外伝』)で作り上げられた世界観を踏襲しながら、『ヴァイオレット』シリーズの最後にふさわしい背景を作ることを心掛けました。僕自身は、美術ボードを描いたり、出来上がった背景素材をチェックしたり、時には修正をしたり、背景としての統括を行っていきました。
――それでは、色彩設計について詳しくお話を伺っていきましょう。『ヴァイオレット』シリーズを通して、色彩設計として大切にしてきたことはありますか?
米田:この作品で一番大切にしているのは「リアリティー」だと思っていて、そう石立監督からも伺っていたのですが……。
石立:え、一番……?
米田:画面作りという点においてですよ?
石立:一番です!
小川:違っていたらどうしようかと思いました……(笑)。
米田:アニメーションにおいては、キャラクターを背景よりも浮き立たせるような色を使うことが多いのですが、『ヴァイオレット』シリーズの場合は写実的な表現を大事にしていたので、キャラクターがより背景に馴染み、本当にそこに存在しているかのようなリアルな色味を目指しました。しかし、暗い場面では光が届く範囲をコントロールしづらいところがあります。ヴァイオレットの時代はそこまで電気が普及していなかったので、本当に電気の無いリアルな暗さに寄せると、暗過ぎてキャラクターが見えなくなってしまいます。さらに、1色その色で塗ってしまったら、1カット内で暗いところから明るいところに出ても色はそのままになってしまうというジレンマが発生するので、とても難しかったです。その辺りの加減については、撮影スタッフと連携して、よりリアルな画面作りを心掛けていきました。
――『劇場版 ヴァイオレット』の中で、特にこだわった部分を教えてください。

米田:ヴァイオレットの手紙を読むギルベルトの夕景のシーンから二人が再会するまでの一連は、特にこだわった部分です。夕日が沈んだ後の月明かりのシーンが見せ場として最高潮に達するように厳密に時間経過を追っていきました。この一連はカットごとに「色変え」を行っているのですが、夕景のシーンは徐々に暮れていくことが分かるように5段階の色を作りましたね。
小川:TVシリーズではありえないことですね(笑)。
米田:そうですね(笑)。あと、月明かりのシーンでは、ヴァイオレットの人間的な重みを表現したいと思っていました。月明りなので、幻想的に青白くしても良かったのですが、やり過ぎるとリアルから離れた雰囲気になってしまうので、ヴァイオレットの経験の積み重ねを色でも表現するためにずっしりとした重さが出るようにこだわりました。
石立:それは初めて聞きました。
米田:いや、言いましたよ! ちゃんと文章で送りました(笑)。そしたら、石立監督は「二人が幸せな感じだといいですね」と言っていましたが、覚えていませんか?(笑)。
石立:はい……。でも、米田さんのお話はその通りだなと思いました。絵コンテの段階で、この月明かりのシーンは、海ほたるとか、夜光虫が飛んでいるような幻想的な雰囲気にしようと思っていました。でも、米田さんの言う通り、地に足をつけて、少しずつ人間らしさを獲得していく実直さを最後まで貫いた上で、きれいだと感じるように落とし込みたいと思い、月明かり以外は特別なことはしないぞ、と決めました。今回は、その辺りを米田さんに形にしていただけていると思います。本当にありがとうございました。
米田:こちらこそ、ありがとうございます。
――美術についても詳しくお話を伺っていきましょう。『劇場版 ヴァイオレット』の制作では、特にどのようなことを意識しましたか?
篠原:背景に注目していただくのも大変嬉しいのですが、実は「背景が良かった」と褒めていただくのは、個人的には少し違うなと思っていまして……。『ヴァイオレット』シリーズで背景スタッフが目指したのは、主役であるキャラクターたちの邪魔にならない背景作りです。この作品における大前提の目標として、「ヴァイオレットの心の成長に合わせて、観ている人にその時その時の情景がそこにいたキャラクターとともに思い起こされるようにしたい」ということを掲げていました。それを基に、美術監督の渡邊(美希子)さんが背景の注意事項を2つ作ってくださって。一つは、「描くものに対して、そのものがどこでどんな人にどんな風に使われていたのかを感じさせるように、時間の流れや、時代の変化が伝わるように、絵として真実味を持たせて描く」ということです。壁の汚れやガラスの傷、地面の轍(わだち)など、細かい描写も深く掘り下げ、リアル寄りだけど絵としてそれらしく感じられる背景を目指していました。そして、もう一つは「空間の広がりと、光を意識し、光源によってできる光のシルエットを実直に追うことで立体感や存在感を出して、キャラクターと一体化した画面作りをする」というところを意識して、取り組んでいきました。
――時代の変化に関して、美術として意識したところはありますか?

篠原:アンの家では、TVシリーズの時代から60年が経過したことで電気が普及し、蓄音機やラジオなどの家電製品が増えています。また、テーブル、椅子、ソファは古くなったので新調し、壁紙も張り替えていますね。大きな家具などはTVシリーズからのものを使用しています。昔からあるものを描く際は、特に経年劣化を意識しました。ライデンの街並みについては、識字率が上がり、街の広告や看板に文字が増えてきています。それから、地面が舗装されてアスファルトに変わり、電気の普及によって電線が配備されています。

小川:電線の有無については、原画スタッフの間でよく話題に上がっていました。あと、博物館になったC.H郵便社が全景で映るシーンは個人的には鳥肌が立ちました。そのくらい好きな1枚です。
石立:僕は、C.H郵便社の正門にある看板のカットが好きです。元々、看板の鎖が垂れた先に手紙とペンのモチーフが付いていたのですが、経年劣化とともに無くなっているんです。看板は会社の顔になる大事な部分ですが、それが崩れ落ちても付け替えることはしていないんですよ。それを見たとき、C.H郵便社としての役目は終えているのだという郷愁が感じられて、好きなんですよね。あと、C.H郵便社内は吹き抜け構造になっているので、光源の取り方やカメラの位置によって絵の見え方が変わりやすいと思いました。背景として、その辺りはどうでしたか?
篠原:ここに光を当てたら格好良く決まるだろう、というカットなりの格好良さを考えながら決めていきました。光源が決まると、自然と絵作りは決まっていったりしますね。
小川:そういえば、今回は影つけなどの光の明暗をしっかり行おう、という話が出ていましたよね。
石立:ありましたね。これは、TVシリーズの頃から気にしていたところでした。画面内の光の方向に基づいて作る影の位置や大きさ、コントラストに関して、仕上げ、背景、撮影スタッフとともに話し合いを重ねました。この作品に関しては、実直に描くことに意味が発生するのではないか、という予測を立てていたので、光の明暗においても写実的な表現を目指していました。『ヴァイオレット 外伝』からは、より一層意識してやりましょう、と話していましたね。背景、仕上げスタッフにはかなり頑張っていただき、本当に作るのが大変だったと思います。すみませんでした!
篠原:お疲れさまでした。
石立:ありがとうございました!
――エカルテ島の背景については、いかがでしたか?

篠原:この2枚は同じ場所の絵で、初めてヴァイオレットがエカルテ島を訪れた時と、60年後にデイジーが訪れた時のものです。道路が舗装されていたり、電気が普及したりと、時代の変化が分かりやすいですね。また、今回は特にエカルテ島の設定がとても細かく作られていました。この世界における島の位置や、人口、気候、植生、産業まで決められていたので、ある意味描きやすいと言えますが、それを実際に存在するように表現するのは大変でした。
――美術設定を作り上げる際、監督と打ち合わせなどは行いましたか?
篠原:美術設定に関しては、美術監督の渡邊(美希子)さんに作っていただいた資料をもとに進めていたので、自分が携わった時には既に出来上がった状態でした。石立監督から見てどうでしたか?
石立:この物語はフィクションですが、僕らが生きている地球上にある土地柄や歴史を調べて、それならこういうものがあってもおかしくないだろう、とか、これは違和感を覚えるのかな、ということを背景スタッフと考えながら進めていきました。また、画面の設計図となるレイアウトを作る原画スタッフにもアイデアを出していただくこともあるので、みんなで同じ目的に向かって知恵を絞って進めていきました。
篠原:今、自分自身もその話を聞いていて、なるほどと思いました。ありがとうございます。
第1部が終了し、登壇者転換のために幕間のトークを行いました。石立監督、小川さん、そしてMCの音楽プロデューサー・斎藤滋さんを交えて、監督と演出についての関係について伺いました。
――『劇場版 ヴァイオレット』では、石立監督と小川さんの間でどのような意見を交わしましたか?
石立:演出はその作品を決定づける上で重要な役目を背負っているので、異なる意見は出てきていましたね。みんなでアイデアを出し合うことに通ずるところはあるのかなと思います。
小川:僕は、監督とのやり取りを一言で言うと「闘い」かなと思っています。もちろん、石立監督の意見を尊重することが大前提にあります。監督が話されることは、もっと大きな何かを体現しようとするためのものだと思いますが、まずは石立監督に自分の感じたことをぶつけてみる、ということが大事なのかなと思っています。作品は企画の段階で出来上がるものではなくて、進化していくものだと思うんです。だから、そういうところで切磋琢磨していきました。僕自身も一人のクリエイターとして、この作品の在り方を具体的にイメージしていきますが、やはり自分にも演出としての考えがあるので、それを石立監督に伝えていきましたね。
――具体的に、お二人で話し合いを重ねたシーンはありますか?
小川:一番、わずらわしかったのはどこですか?
石立:わずらわし……わずらわしくは無いです。……一番しつこかったのは(笑)、ギルベルトがヴァイオレットからの手紙を読むシーンの中に最後の一文が映るカットがあるんですが、そこは小川さんと話し合いを重ねて生まれたものだと思っています。監督という立ち位置だと、最終責任者として決定権を握っているプレッシャーで視野が狭くなってしまうことがあります。小川さんは客観的な視点でプレゼンをしてくれるので、視野を広げてくれたと思います。小川さん、一カ月の間に何度も話しに来ていましたよね(笑)。僕なりの意図を伝えていたのですが、話しに来るたびに納得しない顔で帰って行きました(笑)。3日に一回くらい来ましたよね。
小川:そろそろもう一回言っとこうかな、と思って(笑)。石立監督は渋めにまとめがちなので、僕の意見も一つの判断材料として入っていけたらなという目論みでした。でも、まぁしつこかったですよね(笑)。
石立:(笑)。
スタッフトーク第2部
続いて、第2部に登壇したのは、引き続き、監督・石立太一さん、演出・小川太一さん、そして、撮影監督・船本孝平さん、3D監督・山本倫さんです。
――それでは、船本さんにお伺いしますが、撮影監督とはどのようなお仕事ですか?
船本:お客様が最終的に見る画面を作るセクションが撮影です。背景で描かれた絵、仕上げで色が付いた作画の絵が撮影セクションに届き、それらを組み合わせて最終的な絵にするのですが、ただ合わせるだけでなく、画面全体に雨や雪を降らせたり、光の効果を入れたり、キャラクターなどに対しても様々な効果を加えます。撮影監督は、「この映像で観ていただいて大丈夫」という、映像の最終的なクオリティーのコントロールが仕事となっています。
――続きまして、3D監督のお仕事について教えてください。
山本:3D監督は、技術的な部分と表現という二つの側面から、作品に出てくる3Dに対して考えていく人だと、個人的に考えています。表現だけでなく、技術的な部分で困難な部分もあったりするので、その部分の研究開発も含めて担当しています。
――早速、撮影監督のこだわりについてお話ししていただけますでしょうか。

船本:石立監督が描かれた絵コンテを見てみたら、今回はものすごく海がたくさん出てくる作品だったんです。その海を「じゃあ、船本くん、よろしく!」と軽い感じで言われまして……。できるかわからないところを、まずいきなり「これでいくから」と、言われたんですよね?
石立:そんな軽く言ってません(笑)。
船本:(笑)。最終的に二人が再会するところが海なので、やはりこの場所が一番美しくなることを目指しました。この作品では、噴水も含めて、雨や水たまりといった様々な水が出てきますが、そういった自然現象にも様々な感情表現があると思って作っています。水に限らず、雪が降っていても、しんしんと降っている雪なのか、風に吹かれて荒ぶっている雪なのかなど、キャラクターの心情とそのシーンに合うようにいかに美しく綺麗に作るか、というところをこだわっています。特に、海での再会シーンは、どのシーンよりも一番綺麗に撮りたい!というこだわりがあり、本当に一番最初から制作が終わる最後まで、クオリティーアップを延々とし続けたカットになります。そこを踏まえて、石立監督と小川さん、いかがでしたか?
小川:僕も絵コンテを読みながら「エグいな」と思っていたんです。二人が会う海が、ちょうど浅瀬なんですよね。二人が会うのにちょうどいい場所を考えて、これくらいの浅瀬を選ばれたと思いますが。もう少し深いところだったら、一定の波で描けたのかもしれないですが、浅瀬なので、波が来たり引いたりする表現がすごく複雑になります。その部分を、延々、初期から悩まれていましたよね。
船本:そうですね。波が引き返す部分だけでなく、例えば船が通った後に水をかき分ける波とか、そういう部分も全部制作していたので、海のシーンは苦労しました。綺麗にできたとは思うのですが……。
石立:船本さんが言われた通り、作画の作業が始まる前から、船本さんが仕込みというか、「こういう波の動きはどうですか」と作って見せてくれていたんです。1年以上かけてちょっとずつ、船本さんの中で技術革新がされて。このシーンに限らず、海はたくさん出てくるので、最初はちょっとだけ不安がありました。ここは、寄せては返す波の中に二人が立っている場面だったので、「もし、撮影で上手く作れなかったら、波は作画で描こう」と言っていました。
船本:少しだけですけど、作画で描いてある波もありましたね。
石立:でも、結果的に船本さんが頑張ってくれたおかげでこのシーンが完成しました。撮影の力でここまで海の表現……キャラクターと海の部分のマッチングといいますか、水がリアルすぎてもキャラクターが浮くし、キャラクターに合わせすぎても少しリアリティーが足りないかもしれない、という微妙な表現のさじ加減を本当に頑張って作ってくれて……。僕は本当に何もやっていないので、感謝しかありません。ありがとうございます。
船本:こちらこそ、ありがとうございます。シリーズを通してですが、この作品は写実性を大切にしていました。アニメキャラクターは基本的に単色で塗っていくので、何も処理をしないとペッタリとした平坦な印象になります。本作に関しては、実線の線数が多いこともあり、線の中にも色を入れ、周りの色を線に溶け込ませながら、さらに、線自体も細くしていく、という処理も加えてより背景と馴染むようにしています。背景とキャラクターが同じ空間にあるという表現を目指しました。

小川:線を細くする処理は、すごいですよね。劇場版では、僕たちはキャラクターの絵をB4サイズの紙に鉛筆で描くんです。B4サイズに描いたものを劇場の大きなスクリーンに映すので、必然的に線が太く映し出されてしまいます。対策として、大き目に描いた絵を撮影で縮小して貼り付ける手法(※拡大作画という手法)を用いることもありますが、それでもスクリーンでは線が太く見えるので、船本さんが開発してくれた線を細くする処理は本当にすごいです。うまく馴染んでいて、この作品のクオリティーにすごく寄与しているなと思っていました。

船本:こちらは、撮影で被写界深度……カメラでいう「ボケ」という表現を踏まえて処理をしています。僕たちが作る作品では割と多用される表現で、周りのピントをぼかしキャラクターに焦点を合わせ、観ている人の視線をキャラクターに集中させるという、視線誘導の技法ですね。その処理を行いつつ、光の表現を加え、より情報量をあげる。背景の情報量がすごく多い作品なので、キャラクターの情報量もあげないと浮いてしまいますので、基本的に、ものすごく処理を入れています。このカットですと、髪の毛にグラデーションを入れたり、色と色の間の境界線にグラデーションを入れたり。様々な光の干渉を入れたりもしています。この作品はとても情報量が多く、かつ、綺麗に見えることをこだわりました。
――それでは、3D監督のお話も伺えたらと思います。

山本:写実的な表現を意識している本作ですが、3Dの場合はリアルにしようと思えばどこまでもリアルにでき、実写のように「アニメで浮いてしまう表現」になってしまうので、逆に、写実性を踏まえた「意図した形の表現」に落とし込む作り方を行っています。例えば、車の3Dだと、窓ガラスに入るハイライト部分は、光をリアルに反射させるというより、「こういった形の光を入れるぞ」という意図を持って付け加えています。
また、写実性が強い作品なので、塗りの部分はベタッとしたままではなく、木や鉄といった質感を、作画や背景の雰囲気に合わせるように意識して入れています。

あと、冒頭に登場するヴァイオレットの部屋のタイプライターは、60年後のタイプライターです。監督から「ただ古く汚く感じる表現ではなく」と言われ、普段作中に出てくるものより、アンティークのような少し古びているけれど美しさも保った感じを意識しました。撮影処理で光等も加えてもらうので、光の効果も踏まえた表現になるよう気をつけて作りました。

また、3Dで作った人々などを配置したカットは、ヴァイオレットの世界観、こういう日常風景を、3Dの人々や車などで表現できるように、色々配置しながら工夫をしています。
――3Dのスタッフと作画のスタッフが力を合わせてできたシーンがあるそうですね。

山本:冒頭でデイジーがアンの手紙を読んでいるときに、手紙が舞い上がり、その後手紙が街中を飛んで行き、ヴァイオレットの世界の方に繋がっていくカットがありますが、そこで手紙が人々の間を縫って飛んでいくシーンです。「ここの街並みと人々を3Dでできないでしょうか」と小川さんから相談がありまして……。
小川:そうです。
山本:「いやいや、これはキャラが少し寄りすぎじゃないでしょうか?!作画にしたほうが良いですよ!」と。
小川:譲り合いの精神ですね(笑)。
山本:3Dで頑張ればうまく表現できる部分もあるかもしれないですけれど、これはやはり……。
小川:わかってました、わかってましたよ……!
山本:(笑)。ということで、やはり、作画の豊かな表現力で作ったほうが良いというところで、歩いているキャラクターをどこまで3Dにして、どこまで作画にするかというのを……色々押問答しましたよね(笑)。
小川:だいぶ、やりとりさせていただきました! カメラワークを3Dで作っているので、作画で描くにしてもキャラクターを1枚1枚パースにきちんと乗せて描かないといけなくて。手間的にも一番難しいところだったんです。
そのため、まずは全て3Dでキャラクターを作ってもらい、それを“アタリ”にして上から作画でキャラクターを描き直す、という作業を行いました。これ、何コマ打ちでしたっけ? 2コマ打ちでしたっけ? 確か、そこでも一問答ありましたよね?
山本:はい。ありましたね(笑)。
小川:1コマ打ちだと動きがヌルヌルしすぎたので、じゃあ2コマ打ちか?と試したら、今度はカクカクする……みたいな。それで、1コマ打ちと2コマ打ちのキャラクターを混ぜていたと思います。
――「コマ打ち」について解説していただけますか?
小川:アニメの映像は、1秒間に24コマ(※フレームとも言う)の画像を映して絵が動いて見えるように作られています。制作するときは1秒24コマ(フレーム)のフォーマットで作ります。1枚の絵を何コマ分映すかで動きの見え方が変わり、1枚の絵を1コマで映すなら(=1コマ打ち)1秒間に24枚の絵を描く必要があって、ヌルヌルした動きになります。1枚の絵を2コマで映すなら(=2コマ打ち)1秒間に12枚の絵で動きをみせます。1枚の絵を何コマで映す動きにしようかな、という時に「コマ打ち」という表現をします。

山本:あとは、どこまでのキャラを作画でするのか?というのを話し合ったんですが、結局、この赤丸のキャラまでほとんど作画で対応していただいて……後ろで走っている車も作画で描かれていますよね。
小川:そうですね。作画……ですね(笑)。
――完成した画面で、歩いている人たちがおかしく見えないということは、成功しているということでしょうね。
小川:そう……ですね。最初の段階の打ち合わせでも、「石立監督、ここどうします?」と話してましたよね。
石立:えーっと……例によってその頃の記憶が……(笑)。このシーンは、小川さんが演出してくださっていて、監督はカット袋、いわゆる絵の素材がすべて入っているものの一つ一つはチェックをしないので、僕はほぼ完成した状態で見せていただいて、どうやって作っているのかなと僕自身思っていたんです。これ、ちなみに手紙も3Dで“アタリ”を出したんですか?
山本:いえ、手紙は全部……作画だけですね。3Dの“アタリ”は出していないです。
小川: むしろ、この手紙の作画の動きに合わせて、カメラワークを何度もやり直し……。
山本:このカメラワークに至るまでにまず時間がかかりましたね。原画スタッフにまず、基準となる「手紙の飛んでいく気持ちよい」動きを描いてもらいました。ただ、そのまま作画に合わせたスピードでカメラワークをつけても、線の情報量や見栄えから「気持ちいい飛び方」になかなかできなくて。なので、絵の動きに合わせるのではなく、その雰囲気を自分の中に落とし込み、どういった感じでこの手紙を飛ばしたいのか?というのを考え、それを3Dのカメラワークに落とし込んでいくのが、大変でした。
小川:何パターンか作っていただきましたよね?
山本:ここに至るまで、何十パターンですかね(笑)。車に寄っていく気持ち良さや、そこから舞い上がっていくまでのタイミングだったり……結構細かく、カメラワークについては詰めましたね。
小川:ありがとうございます……!
――では、監督から「ヴァイオレットが書いた手紙」について、お話があるとお聞きしました。いかがでしょうか?

石立:「最初の舞台挨拶で出した宿題」の答え合わせなんですけれども……。ヴァイオレットがギルベルトに書いたあの最後の手紙には意味が込められていて、ちゃんと読めるようにこの作中の言語で作っています。一筋縄では読めないように世界観設定の鈴木貴昭さんに作っていただきました。ただ、解読してくださるお客様もいて、すでに解読されていたような気もしますが……。最後の一文が結局なんと書いてあるのかというと、「私は、少佐を愛してます。」と書いてあるんです。
何故それを手紙に付け加えたのかというと、ギルベルトが終盤のシーンで、今まで「会えない」と力強く言っていたのに、走り出してヴァイオレットを追いかけるに至る。ギルベルトからしたら、今までありがとうございましたというヴァイオレットの感謝の手紙とその気持ちを受けるだけでも、十分気持ちは汲めると思うんですけれど、ただ、もう一声!……先ほど、お話した小川さんと何度も話し合ったところですけれど、もう一声欲しいという部分に、確かにな、と思うところがありました。ギルベルトから「愛してる」と言われ、その言葉の意味をずっと探していた主人公・ヴァイオレットという女性なので、ヴァイオレット自身が、「愛してるを知ったから、愛してるを伝えたいと思いました」ということを、やっぱりギルベルトに対して、何かしらどこかで伝えないといけないなと……。じゃあ、なぜそんな大事なセリフを音として読み上げなかったのか? この作品が、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』というシリーズの集大成という最後の位置付けだったので、作品全体が「観ていただいた方に対するヴァイオレットからの手紙」という構成にしたいと、絵コンテを描く前からずっと思っていたんです。
ですので、デイジーの「パパ、ママありがとう、愛してる」の流れで出る最後の文字「愛してる」は、文字が画面に出る直前にヴァイオレットがモチーフになっている切手を映すことで、「ヴァイオレットからの愛してる」という意味も込めました……。「ヴァイオレットからの愛してる」はどうしても最後に持って行きたかったんです。もちろん、ギルベルトを思う感情もあって、きっと彼女もそれを伝えようとしていたと思います。ギルベルトと再会した海のシーンでは、ひたすら泣きじゃくって言えていませんが、あの場面でもギルベルトに「愛してる」と言ってもらえたことが、自分にとってどれだけ大きかったのかということを伝えるために、ギルベルトに対してヴァイオレットは言いたかったんだと思うんです。でも、あの場で簡単には言えないかなと思ったのと、最後の「愛してる」にどうしても集約したくて。
「愛してる」って難しい言葉じゃないですか。狭くもとらえられるし、広くもとらえられる。ヴァイオレットが、きっと人生をかけて知って伝えた、彼女の中にある「愛してる」という言葉の意味は、すごく大きくて、広い意味になっていると思ったので、男女の「愛してる」に限定して感じて欲しくなかったんです。それは作中のキャラクターたちに対してだけでなく、ヴァイオレットの人生をこうしてともに追いかけ、観てくださった方に対しての「愛してる」という意味も含めた、広義なものであってほしい。だから、ギルベルトへの手紙の所で「愛してる」を音にしてしまうと、男女の「愛してる」に引っ張られてしまう。それは避けたいと思い、音にしませんでした。あの時のヴァイオレットとしては、ギルベルトに対して、手紙という伝達方法でちゃんと自分の気持ちは伝えていたという風にするのが正しいのかなと。これがこの作品にとって一番いい落とし所かなと、小川さんと意見を交わしていた中で最終的に思い至った、というお話でした。
ただ、どう感じていただいたかは一人ひとりの感覚だと思うので、最後は、いかがでしたでしょうか?となりますが……。
一同:(拍手)
――それでは、スタッフトークも終了のお時間となりました。最後に、監督から一言お願いします。
石立:色々ありましたが、作って完成して、これだけ多くの方に観ていただけて、僕ら、制作したスタッフ一同、本当にありがたく、嬉しく思っています。作品としてはひとまず完結させた、と言うとおこがましいですけれど……ヴァイオレット・エヴァーガーデンという主人公が歩んだ道、彼女の人生を、ある程度一つの形にはできたのかなと、個人的に思っています。TVシリーズから数えれば、長い時間、こうして一緒に彼女の人生を追ってくださった皆さまには、もう、感謝しかございません。
作品として、一旦閉じたとは言え、原作の暁先生をはじめ、いろんな方がおっしゃってくださっていますが、観てくださった方の記憶の中、心の中に、何かしらの形で残って、少しでも長く留めていただける作品になっていれば、これ以上嬉しいことはないなと思います。今回観ていただいたドルビーシネマ版が公開され、まだしばらく、本作を映画館で観れる時間があるのかなと思います。もうしばしお付き合いいただきつつ、劇場で観る時期が終わったとしても、皆さまが感じていただいたものが、先の未来に何かしらの形で繋がっていけば嬉しいなと思っています。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました!
――本日は、ありがとうございました。
MC:山田杏菜(京都アニメーション)
MC補佐:音楽プロデューサー・斎藤滋